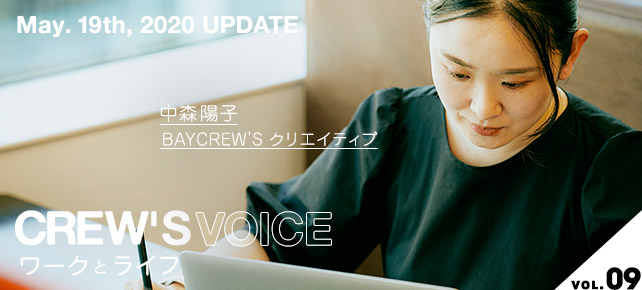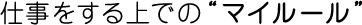Photo_Shintaro Yoshimatsu
Text_Masahiro Kosaka
―
「無闇な効率化より、手数でやれることはしたい」
ベイクルーズ初のリユースショップをわずか3週間で立ち上げた彼は、そう言う。
見かけによらず(失敬)、真面目で頭脳派。
かといってカタブツでもなく、無類の酒好きで、熱い夢だってある。
そんな絶妙なバランスと色気を放つ彼に、ワークとライフについて、聞いてみた。
生命理学の分野から、アパレル業界に。
目の前で誰かが喜ぶ姿が見たかった。
―ベイクルーズ初のリユース業態として、今春下北沢にオープンした新店舗CIRCULABLE SUPPLY(サーキュラブル サプライ)。この立ち上げの指揮を執ったコンセプターの太田さんですが、具体的にはどんなことを行ったのでしょうか?
「プロジェクトの座組や、仕組み作りはすべて担当しました。リリースなど対外系のことも一通り。あとは、ショップ名を決めたりなど。要するに、会社に承認が必要なことはすべてですね。今年の3月に決議が出てから、3週間というスピード感でなんとかオープンに漕ぎ着けました(笑)」

―下北沢といえば、古着屋やリサイクルショップの激戦区ですよね。そんな場所に出店するにあたって、CIRCULABLE SUPPLYの強みはどういったところにありますか?
「まず、店舗で販売するのはすべてスタッフの私物なんです。つまり、プロの服屋が身銭を切ってでも買おうと思ったモノ。そこに、単なるリサイクル商品との明確な違いがあると思っています。加えて店舗空間については、長くベイクルーズで店作りをしてきたからこその、服屋としての編集を行うことができます。たとえば商品陳列。ラックごとに、うちのブランドっぽいアイテムを並べるようにしています。このラックはDeuxieme Classe、そっちのラックはIENA、といったように。あくまで「〇〇っぽい」ということですが、それぞれのラックに意味が生まれる。そうした演出は、ほかのリサイクルショップではできないことだと思います。」

―リユースの業態ではありながら、限りなくセレクトショップに近いというか。様々なグループブランドやオリジナル商品を持っているベイクルーズだからこその店作りがユニークですね。店内レイアウトや陳列なども、太田さんが担当していくのでしょうか?
「いずれは店のスタッフに委ねられるといいですね。ただ、すべて単品勝負でやっていくなかでMDを構築しなければならないので、当面はぼくがやっていくことになるかと。商品一点一点ときちんと向き合って、「このテイストはこれくらいの球数があるからラックを組もう」なんてのは現状データの管理ではできないことなので、しばらくはアナログ運営です。」


―ちなみに、商品は「スタッフの私物」ということですが、全スタッフから集めるとなると膨大な数になりますよね。統制も取りづらそうです。どんなスタッフから集めるかなど、ルールがありますか?
「声がけ自体は、およそ1000人ほどいる本社のスタッフ全員におこなっています。つまり、ヒトでの選定はしておらず、モノでレギュレーションを設定している。基本的にはベイクルーズのオリジナルブランド、仕入れブランドの商品であること、そしてエルメスやヴィンテージのリーバイスなど市場価値があるモノ。実はこのレギュレーションについては、スタッフたちにモノの市場価値を捉えさせる、というこの事業のテーマのひとつが隠されています。「自分が要らないから出す」ではなく、「不要なモノのなかから、いまのお客さまにとって価値がありそうなものを出す」。だから、値付けも出品するスタッフ自身に委ねています。値付けって、商売の基本中の基本であると同時に、極意でもある。それをスタッフに学ばせる構造になっているんです。この事業は利益追従型ではなくて(もちろん利益が出るに越したことはないですが)、スタッフの育成という視点が入っている。あと、拡大可能性を模索するということも。こういったリユース事業が通るのであれば、スケールの拡充もしていきたいと考えています。」
―リユースショップという構造のなかに、実に様々なアイデアやコンセプトが内包されているのですね!それだけの事業をたった3週間で、しかもモノの管理などアナログな面も多いなか立ち上げた、と。一体、どうやったのですか…?
「無闇な効率化よりも、可能であるなら手数を取ることにしています。また、何事もプロセスをじっくり考えるようにしている。何にどれくらい時間がかかるのか。継続的な事業なのか、単発なのか。それからゴールを設定して、ステップを考えて……。今回は、ひとまず3ヶ月のテストマーケティングということが決まっていたので、単発だなと。なら、手数でやったほうがいいと判断しました。」

―そのあたりのバランス感覚って、どこで培ったものなんですか?
「ぼく、理系の大学出身なんです。主にDNAの研究をしていました。どんな実験をするにも、一つひとつ指示書を作るのが当たり前の環境で。仮説を立てて、そこに対してどんなステップを踏むのかをいちど想定してからスタートを切る。その頃の経験がいまの仕事にも活かされているのかもしれません。」
―理系で、しかもDNAの研究とは、ベイクルーズでは異色の経歴ではないでしょうか。元々はアパレル志望ではなかったのですね?
「獣医になろうと思っていた時期もあります。でも、動物の血を見るのが怖いなと…(笑)。それで、動物の病気を治す薬を作ることにした。いわゆる生命理学という分野ですね。でも、日本って薬をひとつ作るにもものすごくハードルが多くて、市販されてお客さんの手に届くまでにはとにかく時間がかかる。ぼくは、目の前で誰かが喜んでくれるのを見たかったんです。そこで、自分の好きな物はなにかと改めて考えたとき、洋服が浮かんだんです。」

―そうして、アパレル業界に入って10年ほど経つわけですが、いまどんな風に感じていますか?
「30歳を過ぎてからの武器って、会社のなかでの認知だったり立場だったりすると思います。外資のコンサルでもなければ、資格があるわけでもないので。長く働いているとみんなネガティブなことを言ったりもしますが、そんな時間があるなら、自社のなかで活躍する術を考えたほうがいいのになって。……なんて、けっこう真面目な姿勢でやっています(笑)」
―最後に、今後の目標について教えてください。
「夢はあります!北海道で農業をすることも面白いのかなと思います。第一次産業って絶対必要だと思うし、ゼロイチでものづくりをして人のためになるって、素敵じゃないですか?」

「大学の頃からノート派。仕事でも、基本的にはノートを使っています。
考えついたことを直感的に書ける。そのアナログ感がいいんです。」
太田篤志郎
CIRCULABLE SUPPLY コンセプター