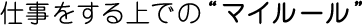Photo_Shintaro Yoshimatsu
Text_Masahiro Kosaka
―
ピース、ハートフル、パワフル、チャーミング…、
どんなポジティブな言葉も、服みたいに似合ってしまう。
「ひとに恵まれてるんです」、と彼女は言うけれど、
その人柄が、自然とひとを惹きつけている。きっとそうだ。
そんな彼女にワークとライフについて、ざっくばらんに聞いてみた。
すごく一途な部分と、新しい出合いへのワクワク。
その両方が、いつまでも楽しいんです。
―まずはVERMEIL par ienaについて聞かせてください。どういったコンセプトのブランドなのでしょうか?
「ベースは、フレンチスタイル。それも、いろんな服を経験した、大人の女性が着たいと思えるスタイルを提案しています。ブランド名には、“箔”や“赤”といった意味があって、それはリップやマニキュアの赤を効かせるというイメージから。モードっぽさ、エグさ、そして色気を大切にしています。なかでも“色気”はわたし自身のテーマでもあります。」

―「いろんな服を通ってきた」というと、まさに武見さん自身がそれを体現していますね。ご自身が大切にしている“色気”とは、具体的にどういったことを指すのでしょう?
「セクシーとは、また違います。わたしは基本的にシャツやTシャツ、デニムといったベーシックなものが好きだけど、年齢とともに体型も変化してきて、20代の頃のようにカッコよく着られない。でも、ヘアメイクや小物づかい次第で、色っぽく着られる。それは、お客さまにお届けするうえでも大切にしている提案です。」

―同じように、バイイングするときの目線や基準でもあるのでしょうか。そのほかに意識していることはありますか?
「そうですね。VERMEIL par ienaのオリジナルアイテムは個性的なデザインが多いので、仕入れはシンプルでペーシックなアイテムを提案しています。ただ、シンプルやベーシックを追求するからこそ、ブランドについては、常に新しい出合いを探している。だから、ブランドの合同展示会が大好き!(笑)」
―そうした出合いのなかで、具体的にはどういった部分に魅かれることが多いですか?
「ブースのカラーリングや素材感、セールスの方の雰囲気になにか他と違うものを感じて、そこから服に入ることが多い。だから、先にググったりはせず、フィーリングですね。そうしていると、たまに不思議な巡り合わせってあるんですよね。実は別のきっかけですでに知っていたブランドだった、とか。そんなときに運命を感じちゃうんです!」

―経験に裏付けされたブレない軸を持ちながら、つねに感覚を更新し続けていくことはとても大変なことだと思います。でも、武見さんはそのバランスを自然と楽しんでいるというか。
「お客さまにお届けするものに関しては、ブレないかもしれません。一途ですね。余談だけど、旦那さんとも17歳の頃から付き合ってるし(笑)。すっごい一途な部分と、都度の新しい出合いがあって、あっという間にいまがある!って感じです(笑)」
―旦那さんとの話、あとで詳しく聞きたいところです(笑) ところで、バイヤー歴15年、ベイクルーズの社歴でいうと今年で26年目という大ベテランなわけですが、そんな武見さんから見た、この会社の魅力とは?
「ベイクルーズって、自分の強みと弱みを教えてくれる会社だと思います。弱みがあるからダメ、じゃなくて、弱みを生かすためにどうすればいいかを一緒になって考えてくれる。事実、同世代のみんなはいまもそれぞれの得意分野で活躍しています。また、見てのとおり優等生タイプじゃないわたしが、いまでもキラキラ働ける会社です。」

―VERMEIL par ienaで一緒に働く仲間には、若い社員やアルバイトも多いと思います。そこにあるギャップはどのように埋めていますか? 武見さんが培ってきたマインドを、どうやって彼女たちに伝えているのでしょう?
「ブランドには20代の子も多いです。でも、VERMEIL par ienaを素敵に体現するのには、年齢は関係ない。素敵なマダムに憧れて、真似をしながらでもいいんです。自分のスタイルにできているか、それがなにより大切なこと。また、たしかにわたしはこの業界での歴が長いですが、わたしが正しいっていうスタンスはまったくありません。たとえばわたしがお店に行って試着するときには、その場にいる若いスタッフたちに、「どう思う?」って聞くんです。トップダウンじゃなくて、いつもディスカッションしながら、ブランドのことはみんなで一緒に考えています。」
―そもそも、武見さんがアパレル業界に入ったきっかけについて教えてください。
「パリへの憧れです。そして、旦那さんのおかげでもあります。わたしは服飾の学校を出ていないのですが、そんなわたしをファッションに導いてくれたのが彼なんです。10代の頃にアニエス・ベーを教えてくれて、それがフレンチスタイルへの入りでした。そのあとリュック・ベッソン監督の『グラン・ブルー』を観たというのもきっかけのひとつ。そして、21歳のときに初めてパリへ行きました。団体バスに乗ってホテルに向かう道中の、あの幻想的な夜の風景はいまでも忘れません。それからは半年に1回、お金を貯めてパリに行くようになって、どんどんのめり込んでいきました。」
―旦那さんの影響力たるや。すごく仲がいいことも伺えますが、それだけじゃなく、まさに人生のパートナーといった感じですね。円満の秘訣は何ですか?
「やさしさの塊のようなひとなんです。彼がすごいんだと思います。」
―では、オフの日も一緒に過ごすことが多いのですか?
「10代の頃からずっと、ふたりでサーフィンをしています。結婚したタイミングで茅ヶ崎に移り住んだので、いまでも休日になると、ローカルの友達とみんなで海へ行きます。」
―都心に勤めながら、海のある郊外に暮らす。いまでこそ流行りのライフスタイルですが、もうずいぶん前からそのように暮らしていたということですね。オンオフで過ごす場所を分けることには、どんな魅力がありますか?
「それぞれの場所に、コミュニティーがある。そのぶん情報の幅も広がっていくし、その二面性が楽しいんですよね。茅ヶ崎の友達とは、年に2回国内外にサーフトリップに行くんです。持って行くものといえば、Tシャツ短パン数組、みたいな世界。アパレルの世界とはまさに真逆。だから、毎シーズンその旅から帰ってくると、ファッションに対する価値観がリセットされる。そうしたギャップも楽しいし、大切なことだと思っています。ラグジュアリーなものに囲まれていると、よくも悪くも馴れちゃうので、感覚が麻痺しないように。ふたつの場所を行き来することで、それが自然とできているような気がします。」

―最後に、5年後の目標について聞かせてください。
「やっぱりバイヤーでいる気がするし、そうでありたい。これから新しい時代に入って、これまでのようなニーズはもしかしたらなくなるかもしれないけど、それでも自分なりに考えて、バイヤーをやっているんじゃないかな。」

「モノを判断する基準は、売れるかどうか、ではなく、
胸がワクワクするかどうか。」
武見 弥生
VERMEIL par iéna バイヤー
---