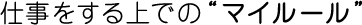Photo_Nahoko Morimoto
Text_Masahiro Kosaka
―
アイウェア専門のセレクトショップEYETHINK HIROB。
コンセプターである彼は、業界の活況を牽引してきた有名店の立ち上げや、
名だたるブランドのディレクションに腕をふるってきた。
眼鏡の可能性をつぶさに見つめ、いわば業界の川上から川下まで。
そして、新ショップを立ち上げて、はや1年。
そのあらましを聞いた。
女性にとっての、
アイウェアのハブになりたい。
―本日はよろしくお願いいたします。仕事やプライベートのこと、マイルールなど、ざっくばらんに聞かせてください!
「じゃあ、さっそくマイルールから(笑)。「反省しても気にしないこと」です。気にせず、前に進む。20年くらい前の『徹子の部屋』で、南果歩さんが言っていたことのウケウリですが(笑)。」
―なるほど(笑)。
「昔は、超神経質で、すごく気にしいだったんです。そこで動けなくなることに、自分の弱さを感じていました。」
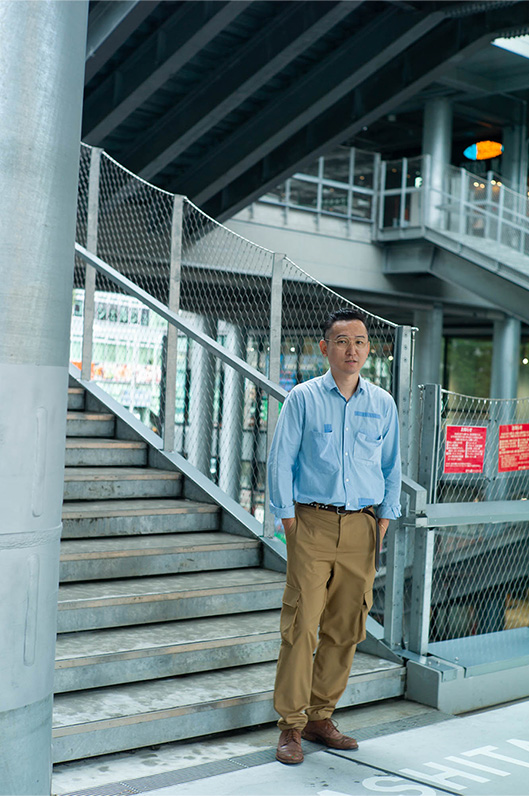
―では、かなり大きくマインドが変わったのですね。
「最初に勤めたイギリス人デザイナーが手掛けるファッションブランドでの経験が特に大きかったと思います。販売をはじめ、アトリエでパターンを整理したり、デザイナーのためにお酒を買いに行ったりと、ほぼ丁稚みたいなことをしていました。でも死ぬほど怒られることが多くて、それで動けなくなり、一回クビになったんです。半年後にもう一度選考を受けて戻ってきて、ようやくまともに働けるようにはなったんですけど(笑)。そこでは、モノを伝える温度や想いといったことも、ものすごく学びました。その経験が、圧倒的にいまのわたしを形成していますね。」

―でも、ファッションブランドに勤めていたとは意外です。なにがきっかけで、服から眼鏡に転身したのですか?

―たまたまというか、眼鏡に特別興味があったわけでなかった?
「いえ、タイミングはたまたまでしたが、むしろ興味はあったんです。実はわたしは目がいいんですけど、15歳の頃からずっと伊達眼鏡をかけていました。」
―伊達なのですね!それもまた意外です。恵比寿にアイウェアのセレクトショップを立ち上げたのは、その後のことということですね?
「そのセレクトショップは、2年ほど働いて退社しました。自分が伝えたい温度や考え方とは、いわば対極のようなものを求められていたし、ちょうど同じ頃、友人と一緒にサロンのようなアイウェアショップをつくる話も持ち上がっていた。そうして、1年後の2002年夏に恵比寿にショップをオープンしたんです。当時26歳の時でした。」
―オープンまでの過程で、印象に残っていることはありますか?
「半年くらいかけて、サロンのイメージを膨らまそうと東京のあらゆる街を巡っていたのですが、あるとき入ったカフェで「あ、こんな感じだな」と唐突に腑に落ちた。空気の流れ、ひとの動き、ちょっとしたスタッフとの会話、それらがすごく心地よかったんです。わたしたちが考えていた、“ハイエンドだけど、カジュアルにリラックスできるサロン”にもぴったりとハマっていました。」
―店舗を運営する一方で、歴史ある英国のアイウェアブランドや日本のファクトリーブランドのディレクションも手掛けてきましたよね。そもそも、眼鏡についての知識などはどのようにして蓄えていったのですか?
「ブランドの方から教わることもありますが、実際に現地へ足を運ぶことも多いです。例えば26歳の頃から、毎年ヨーロッパのほうに行って、倉庫に5000本くらいあるアーカイブをひとつひとつ確かめていく。「これが何年代だから、こういう流れか」と、掘っていく感じです。」

―なるほど。次はEYETHINK HIROBについても聞かせてください。これまで販売、ショップの立ち上げ、ブランドディレクションなど様々経験してきて、2019年にショップをスタートさせたわけですが、どのようなことを意識していますか?
「考え方はさほど変わらず、見せていく側面が違うというか。特に意識していることと言えば、女性が入ってきやすい見せ方や提案。近年女性のマーケットは拡大しているのに、女性が眼鏡を買いやすい場所って、あまりないと思うんです。だから、我々がアイウェアのハブとなって、女性のお客さまに魅力を伝えていきたいと考えています。」
―具体的にはどのような提案をしているのでしょうか?
「例えば、ひとつのモデルでサイズバリエーションを広げて、サイズ遊びをすること。フレームはジャスト、サングラスならワンサイズ上げる、とか。比較的女性らしいシルエットのウェアリングの方であれば、ワンサイズ上げてバランスを取る、とか。また、いいものをシンプルに伝える手段として、色にも注目しています。クリアレンズだけを50本くらい集めてディスプレイしたりすると、「かわいい!」とだけで手にとってもらえることも多いんです。もっとシンプルにアイウェアの楽しみ方を伝えていける事が、ベイクルーズだからこそできる強みではないかなと考えています。」
―サイズやカラーリングは、三島さん自身も普段眼鏡をかけるときには意識しますか?また、眼鏡をかけることの魅力は?
「わたし自身は、シーズンごとでウェアの気分も変わるのでそのタイミングで、好きな形を2色買いして、日によってかけ替えることが多いです。15歳の頃から週末だけ黒ぶちの眼鏡をかけていましたが、眼鏡をかけるだけでスイッチが入る。いまだに、その感覚があります。」
―逆に、スイッチをオフにする、息抜きの方法は?
「最寄りから少し離れた駅から自宅まで歩く。そうやって無の時間をつくるようにしています。あとは、娘とコミュニケーションをとる時間も、割とオフですね。」
―お子さんとは普段どんな風に過ごしているのでしょう?
「この自粛期間中にスケボーをはじめて、いまでは週5で付き添っています(笑)。何か夢中になれることを小さい頃にもてるのはいいですよね。子どもが夢中になっていると、大人まで夢中になれるし。」
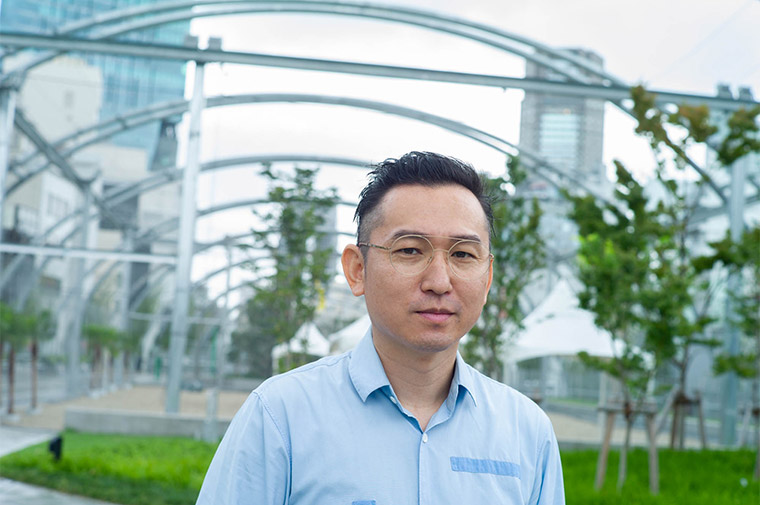
―ちなみに、三島さん自身が夢中になっていることはありますか?オフの日は何をして過ごしますか?
「昔から音楽が好きで、いまでも聴きに行きます。スタジオコーストとかリキッドルームももちろん好きですが、最近は特に、ビルボードやブルーノートといった、食事しながら質の良い音楽聴ける場所に妻と出かけます。お互いジャズが好きなのですが、彼女はアメリカで育ったということもありヒップホップやR&Bから、わたしはロックから、と入り方が違う。それだけに、ジャズといってもかなり幅広く聴いています。」
―音楽が、仕事やものづくりのインスピレーションの源になったりもしますか?
「ファッションと音楽は、若い頃から密接だったかもしれません。その延長線上にライフスタイルがあったと思います。10代の頃にヒップホップにハマって、歯を全部金歯にしようとしたり(笑)。ジャズをメインで聴くようになった20代の頃は、いまでも仲良くして頂いている松浦俊夫さんが当時在籍していたUFOのスタイルに憧れ、スーツに革靴でクラブに行っていました。眼鏡をかけはじめたきっかけも、同じく音楽や映画から。そこがはじまりでした。」

「反省しても、気にせず前進する。」
森山 智美
Plage マーチャンダイザー
---