



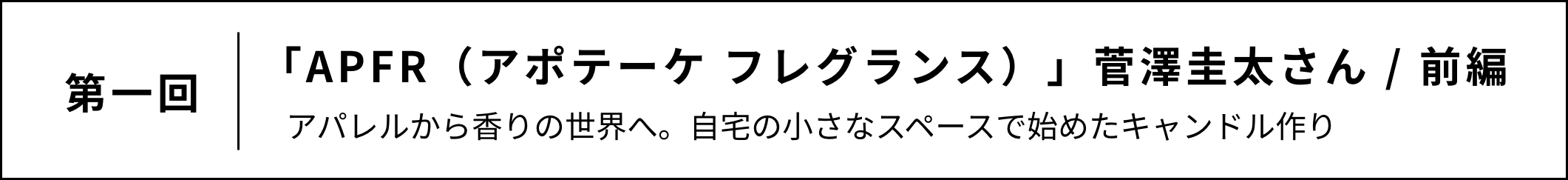
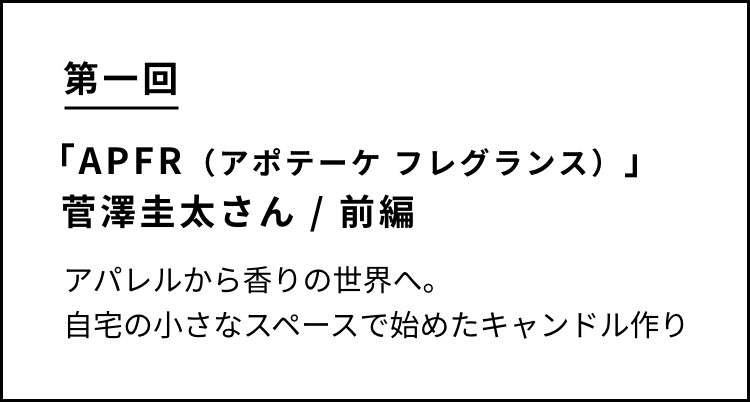
人気のモノには、ワケがある。
JOURNAL STANDARD FURNITUREで売れているアイテムのルーツを辿る、新企画が始まります。
第一回は、ハンドメイドにこだわりを持つ国内屈指のフレグランスブランド「APFR(アポテーケ フレグランス)」。
最近お引っ越ししたばかりという新拠点のLABOで、創業者でありクリエイティブ・ディレクターの菅澤圭太さんにインタビュー。
ブランド設立の過去からリブランディングを果たした現在、そしてこれから描く未来まで、たっぷりうかがいました。
前編は、菅澤さんの香りとの出会いから、ブランドを立ち上げるまでのエピソードをお届けします。―――まず始めに、菅澤さんのこれまでの経歴を教えてください。
最初のキャリアはアパレル業界です。クラブDJをやっていた趣味のツテで、ブランド営業の仕事をしていました。海外に行く機会も多かったですね。ある時に中東諸国を訪れた際、現地の独特な香りの文化に触れたことがあって。彼らは宗教上の理由で、香水ではなく香油を使うんですね。アラブ諸国で使用されるバフールと呼ばれるお香や、香木、スパイスもたくさん並んでいる様子なんかに刺激を受けて、これを日本でやりたいと思いました。ただ、そのまま持ち込んでも中東と日本はカルチャーが大きく違う。香り付きのキャンドルから始めたいと思ったのが、ブランド作りのきっかけです。

フレグランスといえば、その頃は海外のビッグメゾンがこぞって出していましたが、ルームフレグランスというジャンルはまだ少なかった。国内では、柔軟剤が話題になったくらいで、香りアイテムが今のように浸透していませんでした。
当時、キャンドルといえば、カラフルな造形キャンドルが流行していたので、それと同じことやるのかと友人には言われていました。当時のフレグランスキャンドルは非常に高価なものが多く、購入してもディスプレイになっていたので、中間の価格帯で販売できるキャンドルを作りたいと考えました。
まだ市場が広がっていないジャンルだったからこそ、魅力を感じましたね。昼はサラリーマン。
夜はキャンドル作りに試行錯誤の日々アパレル業界には27歳まで身を置いていました。その後、諸事情で合成樹脂の原料商社に就職することに。アパレル業界時代は割と自由にやらせてもらえていたので、社会人としての常識が全く足りず、転職当時は上司に毎日のように叱られていましたね。けど、この転職で色々なスキルが身につき、とても勉強になりましたし、感謝しています。
その会社は総合商社で、企画開発や売り込みも自分でやらせてもらえて。ただ、最終的にどんな製品になるかわからない原料も売るので、洋服の時のように使ってくれるユーザーが見えづらかった。30歳が間近に迫った頃の話です。この先の将来に悩んでいた時期と重なり、自分でモノを作って売りたいなと思うようになりました。そこで、キャンドル作りを独学でスタートしました。
―――どうやってキャンドル作りを?
最初は、実家暮らしをさせてもらっていたので、自分の部屋の8畳くらいのスペースで始めました。出来合いの香料を購入してワックスに混ぜ込んで作ってみたものの、全然うまくいかなくて。知識もないままでしたので、知らない間に危険物を大量に混ぜてしまい、キャンドルに火をつけるなり全体が燃えて、家族を驚かせたこともありました(苦笑)。もうお手上げ状態でしたね。そこで30歳の時に思い切って、香料の原料会社に転職したんです。
当時は、香りが有機化学だということすら知らなかった。自分がやろうとしていたことの根幹である香り=香料に関して無知すぎました。初めての工場勤務と同時に有機化学を勉強し、原理と工程を学んで。この経験が、今の仕事に大きく活きることになりました。転職した翌年、自分のブランドを立ち上げました。少しずつお金を貯めて、材料を買っては試作を繰り返す日々。ブランドとして何を作りたいか、固めていきましたね。
―――自身でブランドを立ち上げる際、大事にしたことは何ですか?
ハンドメイドで少量生産するスタンスですね。生産からパッケージまで、自分たちの手で全部作ること。感度の高い方々と一緒に、納得のいくものを国内で販売できればいいなと。設立した当時は、アメリカのブルックリンなどで小さいファクトリーブランドが話題になったり、ポートランドの地産地消の取り組みだったり、小さな規模の高感度なモノづくりがクローズアップされていた。自宅のスペースでモノづくりをしている人たちに、刺激を受けたのを覚えています。

“香り問屋”のような存在として、
広いラインナップから気軽に選んでもらいたい―――最初に作ったキャンドルは何ですか?
「24K Rose」(ローズブーケやマリーゴールドといった花々をブレンドしたフローラル・グリーン調の明るい香り)です。創業した年は、5種類くらいキャンドルを作りました。当時はパッケージをブラックで統一していて、男性ウケするフレグランスブランドを意識していましたね。でも1年ほどで飽きちゃって、ユニセックスなデザインに変更しました。

現在、香りのラインナップは38種類あります。イメージしやすい植物をピックアップし、自分なりにどう解釈するかテーマを決めて、香りを調合していきます。例えばローズだったら女性が好きなイメージですが、男性が好むローズはどんな香りだろう?どんなキーワードを組み合わせよう?と深掘りしていく。
こうして香りのラインナップが増えていき、60種類くらいになったこともありました(笑)。でも、自分がかつてインスパイアされた中東のお店はもっともっと種類がたくさんあった。アポテーケも、“香り問屋”のような身近な存在でありたいなと。あまりシグネチャーフレグランスにこだわらず、絞りすぎず、気に入った香りを気軽に日常に取り入れてもらいたいという思いがありますね。
―――豊富なラインナップはアポテーケの魅力の一つですね。中でも特に菅澤さんがお気に入りの香りはありますか?
個人的に思い入れがあるのはs「Maghreb Bukhoor」(マグリブバフール。モロッコにインスピレーションを得た異国情緒ただようオリエンタル・ウッディーな香り)ですね。中東のモスクなどを巡りながら、面白いと思ったカルチャーを自分なりに表現した、思い出深い香りです。
キャンドルから始まり、ルームスプレー、インセンス、リードディフューザー・・・とカテゴリーが増えていきました。特にインセンスは製作するのにスペースが必要なので、だんだんと自宅では手狭になって。新たに工場を構えてアイテムを広げました。
LABOは、書籍などの資料をはじめ香りのインスピレーションにつながるものも並ぶ。
―――香りも商品カテゴリーも増え、好調にビジネスを進められていったのですね。
ありがたいことに取引先は増えていきましたが、最初から順風満帆だったわけではないです。創業したての頃はまだ、香料会社にも在籍していたわけで。その会社ではトータルで7年働きました。創業してしばらくは、17時までサラリーマンして、その後、夜中の3時近くまで自分のキャンドルを作る日々。当然、昼間に営業をかけるわけにもいかず、メールのやり取りも滞ってしまう。どうやって売り込もうかと考えていました。ACMEさんと取引するきっかけは、友人の結婚式だったんです。

前編はここまで。後編はACMEとの取り組みや3月に行ったリブランディング、その先に目指す未来について語っていただきます。

菅澤 圭太
Keita Sugasawa
1980年、千葉県生まれ。
アパレル、商社、香料会社など様々な仕事を経験後、独学で勉強し、ルームフレグランスの制作を始める。2011年に「APFR(アポテーケフレグランス)」を設立。―――
APFR TOKYO
世田谷区北沢3-19-20 reload1-5
03-5738-8641APFR(APOTHEKE FRAGRANCE)instagram →
―――
APFR(APOTHEKE FRAGRANCE)PRODUCT PAGE →
JOURNAL STANDARD FURNITURE ONLINE SHOP →
ACME Furniture ONLINE SHOP →―――
PHOTOGRAPH:Yuma Yoshitsugu
TEXT:Chikako Ichinoi