アーティスト、ミュージシャン、フォトグラファー、デザイナー……。表現を生業としている彼らの装いは、作品のエキセントリックさに反して意外にも、なんの取り留めもないことが多い(例外はいるが)。 しかし、彼らが生み出した表現物との関連性に思いを巡らせてみると、ずいぶんと見え方が変わってくる。
この連載では、画家の小磯竜也さんとともに「表現者と装いの関係」を、彼らの人生や作品と照らし合わせながら考察していく。ライフスタイルとファッションの強固な結びつきは今や言うまでもないことだが、彼らはそれを、いち早く体現していたのかもしれない。 道端から色を拾い、絵を描き、服を着る。第5回は、高田渡と彼の装いについて。
絵・文 小磯竜也
編集 重竹伸之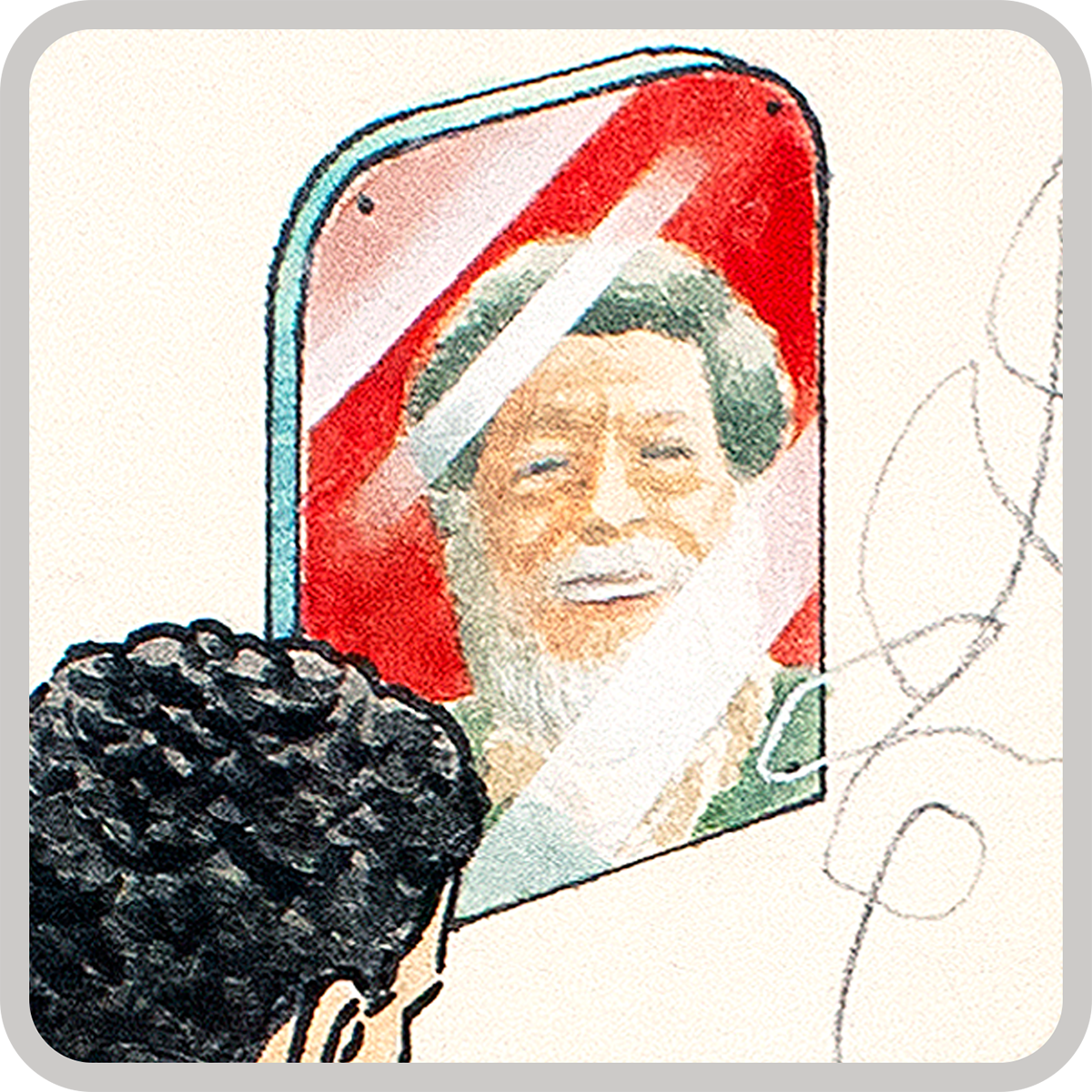
高田渡 Wataru Takada
フォークシンガー1949年岐阜県生まれ。1967年頃からフォークシンガーとして注目されはじめる。日本語の詞をつけたアメリカのプロテストソングや自作曲をレパートリーにライヴで活躍。1969年にはURCレコードの第1回配布アルバム『高田渡/五つの赤い風船』を発表。その後も『汽車が田舎を通るそのとき』『ごあいさつ』などの作品をリリースし、コンスタントにライヴを開催。1971年には「武蔵野タンポポ団」を結成。多くのミュージシャンに敬愛されながら活動を続ける。2005年に惜しまれながら他界。
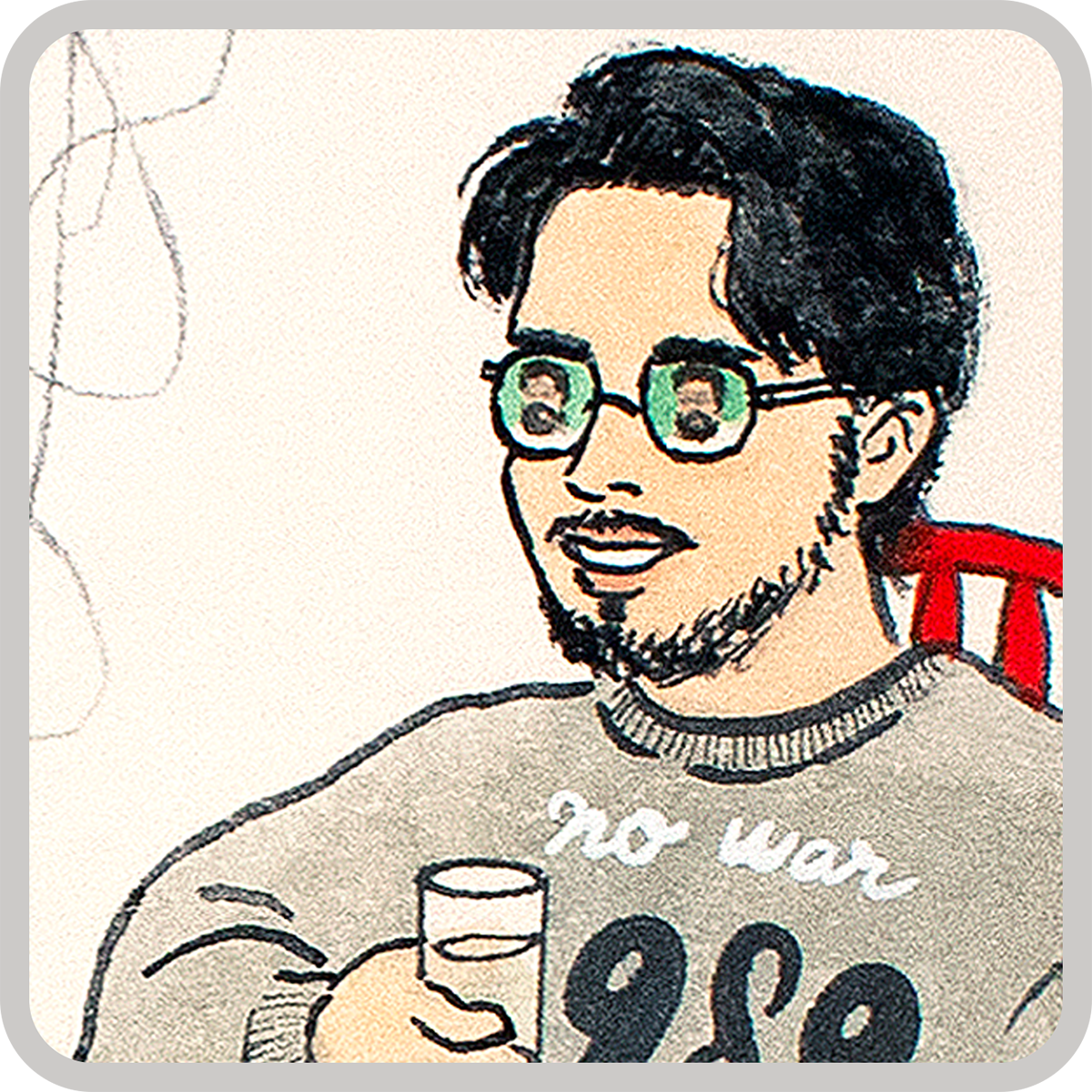
小磯竜也 Tatsuya Koiso
画家 / アートディレクター / グラフィックデザイナー1989年群馬県館林市生まれ、東京都在住。東京藝術大学絵画科油画専攻を卒業後、フリーランスの絵描き兼デザイナーとして活動を始める。2015年に中山泰(元Work Shop MU!!)の事務所を訪問。面白い本などを見せてもらい刺激を受ける。 Yogee New Wavesや藤原さくらなど、ミュージシャンのジャケットアート、ポスター、グッズイラストなどを手がける。
生活と表現の段差
長いことヒゲを剃らない間に顔は丸くなるし、いつか行こうと言ってる間に好きな喫茶店は閉じるし、仕事が忙しい忙しいと言ってる間に大事な人はいなくなったりする。
僕が美大受験予備校に通っていた浪人生の頃に一番大事にしていたのが[作業着に着替えず、家を出たままの格好でアトリエに着いてすぐ絵を描く]という謎ルールだったのだが、酔っぱらって酒を持ったままステージに出てきて弾き語りを始める高田渡は、僕にとって理想の姿である。生活と表現が地続きで、まるで客席とステージの段差が無いみたいなのだ。
ファッションのメディアに高田渡のことを書く違和感に薄々気付きつつも、ここに僕が文章を書いてること自体が不思議なわけで、まあいっかと開き直って書くことにする。渡さんが生きてるうちにその歌に出会いたかったし、演奏も生で聴きたかったし、できれば京都のイノダコーヒーか吉祥寺のいせやで一緒に飲みたかった。

©Tatsuya Koiso
豆腐が衣をまとうそのとき
僕が高田渡を聴き始めたのは浪人生のとき(2008年頃)で、きっかけはYouTubeだった。中学〜高校時代まで僕のヒーローはマイケル・ジャクソンだったので、そこから派生してモータウンの色んな曲を聴いたり、ジェームス・ブラウンの最後の来日公演に父を誘って行ったりもした。ところが浪人生になり受験の不安に押しつぶされ、追い打ちをかけるように彼女にもフラれた僕の心は豆腐だった。みぞおちがワクワクするサウンドや魔法のようなライブパフォーマンスの刺激に豆腐は耐えられない。今の自分の生活に寄り添ってくれる日本語の表現に飢えていた。
それでYouTubeで日本のフォークシンガーを聴き漁っている時に偶然出てきた高田渡の「生活の柄」のライブ映像を見てから、僕の心は詩という衣をまとって揚げ出し豆腐程度には崩れにくくなった。これについてはYouTubeのおすすめ機能に感謝せざるを得ない。あのときはありがとう。
「生活の柄」は詩人の山之口貘が書いた同名の詩を高田渡がアレンジし、曲を付けた歌だ。高田渡は父が詩人で、自身も詩を書くし初期の歌は自ら作詞作曲したものが多かったが、アルバム『ごあいさつ(1973)』の頃から日本の現代詩とアメリカのフォークソングを組み合わせる作風を確立していく。(このアルバムのバックバンドははっぴいえんど! ジャケットアートは湯村輝彦と河村要介!)ちなみに2016年のガリガリくん値上げの際のCMで流れていた「値上げ」もこのアルバムの収録曲だ。
詩が、文字としてではなく声に出して読まれた時に耳から入って広がるものがある。文字で読むと理解できるけど音になるとわかりづらい表現は平気で書き直す。そして詩が歌になるために、ミシシッピ・ジョン・ハート、カーター・ファミリー、ウディ・ガスリー、ピート・シーガーなどを下敷きにしたスリーコードのシンプルな曲が付けられる。高田渡は詩が耳から入ることをとにかく追求した人だ。自分の内側から湧き出てくるものが個性だと信じていた19歳の僕に、引用したり組み合わせたりすることで新しいものが生み出せると教えてくれたのは、ポップアートでもヒップホップカルチャーでもなく高田渡だった。

©Tatsuya Koiso
ノンフィクションスタイル
僕の祖父は大工だった。祖父は自分の娘(僕にとってのおば)の家を1年かけて1人で建てたらしく、そんなこともあって僕は昔から[職人]に対して強いリスペクトと憧れを持っている。ちょっと前に近所のワークマンで「このワークパンツすげーポケットある! カバン持たなくていいレベル!」とテンション上がってレジに並んでいたら、自分の前で会計してる頭に手ぬぐいを巻いたおじいさんがガチ職人のオーラを放っていて「ホンモノ、カッケ〜…」と思った。必要な物を買い揃えているんだというその背中。と同時に己の生まれ年のワッペンがついた帽子をかぶってレジに並んでいる自分のニセモノ感に恥ずかしくなって、僕なりに精一杯の職人っぽい目つきをして会計を済ませた。(もちろん職人じゃなくてもワークパンツは買ってよい)
それで言うと高田渡の装いはどう見てもノンフィクションというか、ありのままだな! と思う。ぼーぼーのヒゲに、シンプルなチェックのシャツ(たまに総柄の派手なシャツ)、寒い時期はその上にセーターを重ねるくらい。ステージに上がるからといって、普段と違う格好をする気配がない。
1960年代前半、日本でもビートルズやボブ・ディランの人気が出始めた頃、高田渡の興味は時代を遡るようにルーツミュージックの方へ向いていた。ブルースやフォークソング、マウンテンミュージックなど、移民たちが各地から持ち込んで歌い継いだ労働歌である。
高田渡が強い影響を受けたウディ・ガスリーは、自らも移動労働者として放浪生活を送っていた経験があり、そこから貧しい民衆の生活を歌にした。前述の「生活の柄」の原詩作者である詩人の山之口貘も、若い頃から職を転々としながら公園で寝るといった日々を送り、「生活の柄」の一節“歩き疲れては、夜空と陸との隙間にもぐり込んで寝たのである”は実体験からきている。また、高田渡の代表曲「アイスクリーム」の影響元でもあるミシシッピ・ジョン・ハートは、若い頃にオーケーレコードというレーベルで13曲のレコーディングをしたが商業的には成功に恵まれず、それ以降は故郷のミシシッピ州アバロンで農民として働いていたが、ブルース研究家のトム・ホスキンズによって再発見されて一躍[伝説のブルースマン]として脚光を浴びる。なんとそれは70歳になってからのことだ。そして高田渡自身も、幼い頃より家を転々としながら極貧生活を送り、中学校を卒業後は印刷会社で文選工(活版印刷の工程で手書きの原稿に従って活字を拾って組む技術者)として働いていた経験を持つ。
労働者の歌を労働者が歌う。詩も、曲も、話す言葉も着る服もぜんぶノンフィクションなのだ。
自分の話に戻るが、喫茶店で働きながら小説を書いてる知人が「小説を書いてる自分こそが本当で、喫茶店は自分の本当の居場所じゃない」というようなことを言っていて、僕はそれは違うと思った。小説を書いてる人間が喫茶店で働いてるんじゃなく、喫茶店で働いてる人間が小説を書いてるんじゃないか。僕自身、しんどい仕事も楽しい仕事も日々あるし、「なんでおれこんなことやってんだろう」と思うときもいっぱいある。人間関係で悩むこともある。でも、そのどれもが自分の本当で、生活より前に表現者としての自分がいるなんてことはありえない(と僕は思っている)。
……最後に、高田渡の著書「バーボン・ストリート・ブルース※」の中の大好きな言葉を引用しつつ、渡さんがお父さんの詩に曲をつけた「火吹竹(アルバム『石』に収録)」と、息子の漣さんのことを歌った「漣(アルバム『FISHIN' ON SUNDAY』に収録)」を聴いて今日は寝ようと思う。渡さん、天国でもお酒飲んでますか。
“僕は、ほんとうの詩というものは、「最後に出さざるを得ない、厳選された一句」だと思う。”
※「バーボン・ストリート・ブルース」
著:高田渡
発行:山と渓谷社 (2001年)担当編集より
BAYCREW'Sのアイテムで高田渡になるなら
高田渡さんには、赤ベースの柄シャツをいつも着ているイメージを個人的に持っていました。ゆるいムードの柄シャツは、イギリスの百貨店が生産しているオリジナルのテキスタイルを用いたJOURNAL STANDARDの春夏の新作アイテムです。
かわいらしさもありつつ、酒飲みのおじさんが着ていそうなポップな怪しさも持ち合わせたボタンダウンシャツは、都会にも下町にもよくなじみそうです。(重竹)



