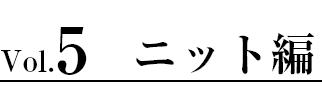Interview
洗濯は、おもしろい。
洗濯ブラザーズ・茂木康之が見据えるアパレルとクリーニングの未来洗濯は、おもしろい。洗濯ブラザーズ・茂木康之が見据えるアパレルとクリーニングの未来

皿を洗い、掃除機をかけ、洗濯機を回す。いずれも、楽しいと思ってやっている人は、どちらかというと少数派だろう。どうせ一生やり続けるのなら、そのひとつひとつの家事を、もっと楽しく、前向きな気持ちで取り組めるものにしていきたい。そのためには、どんなことを知り、どんな考え方で、どういう行動をすればよいのか。
『モノカタル』第5回のゲストは、当連載ではすでにおなじみであろう、洗濯ブラザーズの次男・茂木康之さん。今回は、ニット編。なぜニット編で彼らに話を聞いたか。洗濯難易度の高いニットをフィーチャーするこの機会が、彼らの話を聞く絶好の機会だと思ったからである。蓋を開けてみて気が付いたのは、洗濯ブラザーズが洗濯を通して啓蒙したいのは、もっと根本の話なのかもしれない、ということ。
クリーニングショップ・LIVRERを運営する傍ら、書籍や動画を通じて“自宅でできる”正しい洗濯方法を世に伝えていく彼らの成り立ちから、お洒落を楽しむこと、アパレル業界と手を取り合った先の未来の話まで。
Photo,Text&Edit_Nobuyuki Shigetake
職人技としてのクリーニングを世に伝えたい
横浜市と世田谷区三宿でクリーニングショップ・LIVRERを運営する洗濯ブラザーズだが、洗濯を生業としたのは、今回お話を聞かせてもらった茂木康之さんがアパレル系のテキスタイル修繕会社、クリーニング機器販売のメーカーに従事していたことがきっかけだったそう。
「クリーニングとは、コミュニケーションである」と語る茂木さんは、日本特有の広がり方をするクリーニング業界に対して疑問を抱き、一方では希望を見出していた。それは、人々の“クリーニング屋選びの基準”が明確でないことへの気付きに、端を発する。
ー 世の中にクリーニング屋はたくさんあれど、家の近所のクリーニング屋を見渡してみても、ここは何ができて、何ができない、みたいなことは明確に理解できていないような気がします。
茂木康之(以下、茂木):そうでしょうね。僕たちみたいに技術や知恵をオープンにしているところも少ないですから(笑)。でも、それには理由があって、クリーニング屋の社長、経営者さんって、職人気質な人が多いんですよね。どうしても伝えベタなところがあって。専門性が高い作業も多いので、お客さんに伝えづらいんでしょうね。
ー それって、そもそもこちらに知識が備わっていないことも原因のひとつですよね。
茂木:そのとおりで、お客さんも普段利用しているクリーニング屋のどういった部分が優れているのか、なぜ自身が選んでいるのか、明確な理由を持っていないことが多いんですよね。なんとなく接客が気持ちいいとか、家から近いとか、そんな理由で選ぶことが多いように感じます。
ー 確かに、そうかもしれません。
茂木:言ってしまえば、クリーニングって「やっていることはどこも一緒でしょ?」と思われがちなんですよね。でも、すべて違いますね。
ー これだけ街中に存在しているクリーニング屋のそれぞれが千差万別であり、そこが面白い点であると。
茂木:はい。どういう手法でクリーニングをするのか、何に重きを置くのか、社長の考えやこだわり、すべてがそこのクリーニング屋の洗濯に反映されています。何が得意なのかとか、これは得意ではないけどこうやって解決するとか、そんなことですね。その違いをもっとしっかりと伝えていくべきだと思ったし、自分たちなら伝えられると思いました。
ー モノづくりする上でのクラフトマンシップと重なるものがありますよね。
茂木:まさしく。人は物事の成り立ちを知らないと、面白いとは感じられないんです。知ってもらうためには、まず自分たちが質の高いクリーニングサービスを提供しなければならないなと。具体的にどういったことをしているのかを、しっかり説明していかなければな、と思ったんですよね。
ー そこで、早速店を構えよう、ではなかったんですね。
茂木:最初は訪問営業からスタートして、車1台だけ買ってひたすら街を走り、ドアチャイムを鳴らしまくってましたね(笑)。「洗濯でお困りのことはありませんか?」って。断られることも多かったですが、洋服についての相談役、という感じで、じっくりとコミュニケーションを取りながら。

ー そういった草の根活動的なところから現在のように横浜市と世田谷区三宿にそれぞれ店舗をオープンし、自社ブランドの洗剤をリリースするに至るには、どういったきっかけがあったんですか?
茂木:いまのサイズ感でビジネスができるようになったきっかけとして、ひとつ大きな出来事を挙げるとしたら『劇団四季』や『シルク・ドゥ・ソレイユ』といった舞台衣装のクリーニングを担当したことでしょうね。彼らって、衣装のデイリーケアも自分たちでしているんですよ。色が抜けてしまったらヘアスプレーで染めるし、ときには簡単な洗いもします。僕らが担当したのは、それでは対処できないほどの汚れや摩耗があった際、もしくは長い公演を終えたインターバルでの、大規模なメンテナンスですね。
ー 舞台衣装となると、基本的にはすべて一点モノですよね。
茂木:もちろんです。それに、ああいった衣装って洗う前提で作られていないんですよ。素材や縫製、加工などもいわゆる一般的な洋服とはまったくの別物で。だから、クリーニング屋さんの大半が、どう扱えばいいのか分からないと思いますし、僕も最初は分かりませんでした。一度は断っていますしね。
ー あ、そうだったんですね。
茂木:やってみたい気持ちはあったんですが、断らざるを得なくて。明らかに難易度が高かったし、迷惑かけちゃうのが怖かったんです。でも、これまでにもクリーニングの営業で、難しいとされている修復をしっかりと成功させて、お客さんからの信頼を得られていた自負もあって。自分たちとしても、この舞台衣装の領域に足を踏み入れることで、技術はもちろん、信頼度がアップするのでは? と思ったのは正直なところです。洗えないとされているものが洗えるようになったら、クリーニング屋として完璧じゃないですか。これは何かのきっかけかもしれないと思い、やっぱりやらせてください! と。
ー 「ここにしかお願いできない!」って技術を増やせたら、かなり強みになりますよね。
茂木:そうなんですよね。それに、スーツやシャツといった、一般的に販売されているものだけをクリーニングしていると、そのうち、たくさんの量をさばかないとビジネスとして成立しなくなるな、と思っていたところもあります。
ー 舞台衣装のクリーニングについて、具体的にはどういった工夫をしたんですか?
茂木:まず、水から考えました。殺菌力の高いオゾン水というものを使用しています。どのような効果があって喜んでいただけたかというと、においがほぼ完全に無くなるんですよね。着用するなかで付いてしまったにおいはもちろん、ドライクリーニングで生じる石油系のにおいも無くなったと。舞台衣装を着る演者たちはそれを心底求めていたようで、我々としても長年追い求めて、ようやく辿り着いた技術です。今もいろんな舞台衣装のクリーニングを担当していますが、やはりどれも洗うことを前提としていないので、すごい衣装がたくさん届きますよ(笑)。
誰かにとっての、最後のクリーニング屋になりたい
ー 茂木さんたちが運営しているクリーニングショップ・LIVRERは、クリーニングサービスのほか、店頭で洗剤や周辺機器も販売しています。クリーニング屋さんがオリジナルの洗剤を作るって、これまでに見たことはありませんが理に適っていますよね。
茂木:自分たちで作るまでは市販されている業務用のものを使用していたのですが、なんかどれもイマイチだなと(笑)。洗浄力は良いけど使っている成分が嫌だな、とか、香りが要らないな、とか。逆に成分も香りもクリアしているけど、洗浄力が足りない、とかですね。
ー あくまで自分たちの仕事をやりやすくするために、開発されたということですね。
茂木:そうなんです。だから、もともと販売するつもりはなかったんですよ。自分たち用に作って、使っているうちに「家でも使いたい!」とたくさんの反響をいただいて、じゃあ販売してみようか、と。
ー 高い技術の次は、より良い材料が必要であると。
茂木:すごくこだわってるお寿司屋さんがネタを追求した結果、自分で釣りをしちゃう、ってのと同じことかなと思っています。「この時期の石川県のあの魚が美味しい!」とかいって、どうしてもお客さんに提供したくて、自分で釣ってくる、という感じで。僕が飲食業界の人間だとしたら、多分畑から作りますね(笑)。そういうマニアックな人、飲食業界に限らずたくさんいると思うんですよね。
ー いわゆる一般的な洗剤と比較して、少し値が張りますよね。
茂木:僕らも「ちょっと高いかも」とは思ってましたが(笑)、思いのほかニーズがあることが分かり、嬉しかったですね。
ー 洗剤がよく売れる、ということは、みなさん、ご自宅で洗濯したいという気持ちが根本にはあるのかなと。
茂木:そういう人がすごく増えていってます。日本人の性質として、自宅での洗濯が根付いているんでしょうね。とはいえ洗濯って常に、嫌いな家事ランキングの上位だと思うんです。ただそれは“普段の洗濯”であって、気に入ってる洋服の洗濯であれば、嫌いな人は少ないように思います。
ー 確かに、むしろ気分がいいですね。
茂木:そうおっしゃる人が多いです。大事に着たいからこそ、多少お金をかけて良い洗剤を使う、という考え方ですよね。お洒落が好きな方は洗濯のモチベーションが高い人が多くて、LIVRERのお客さんは「これは家でどうやって洗えばいいの?」って、めちゃくちゃ聞いてきます(笑)。

ー 特に三宿のエリアは、洋服好きな方が多そうだなと思います。
茂木:多いと思います。それと、どちらかというと通勤や遊びに行く街でなく、住む街なんですよね。ここが結構大事で、クリーニング屋は、地域に根付いたサービスなんです。この三宿という地域に住んでいる方々が、リブレがあるおかげで愛着のある洋服が長持ちしたと思ってもらえて、生涯を終えていただくのが理想ですね。
ー その人にとっての最後のクリーニング屋さんになる、というか。
茂木:そうですね。クリーニング屋って、そういう商売だと思います。少し話は逸れるのですが、以前にとあるお客さんが「人生を豊かにしたいなら、まず、信頼できるクリーニング屋さんを見つけることだ」と話してくださったことがあって、すごく印象に残っています。そのお客さんは洋服が大好きで、人生の中でファッションを特にメインに置いていて、大切な洋服をたくさん持っているけど自分ではケアをできないから、腕の良いクリーニング屋さんを近所に、絶対に見つけるらしいんです。
ー 面白い話ですね。
茂木:その人はいわゆる転勤族だったりして、なかなかひとつの土地に留まることができないようで、引っ越した先では、美味しい飲食店を見つけるより先に腕の良いクリーニング屋さんを探すんですって。そのために白い服を近所一帯のクリーニング屋に出して、どこが一番綺麗に仕上げてくるか、テストをするんです。すごく賢いやり方だなって(笑)。
ー なるほど(笑)。出せばわかるものなんですね。
茂木:明確にわかりますね。クリーニングってクチコミが少ない業界なのですが、それには理由があって、混んだり、時間がかかったりするようになることを嫌がるんです。だから、みなさんいろんな方法で僕らを試してみたり(笑)、僕らとしても、心を掴むためにはどうしたら良いのかを考えたりしながらやっています。
ー LIVRERにも、リピーターさんがたくさんいらっしゃいますよね。
茂木:ありがたいことに増えてきましたね。みなさんとてもこだわり屋さんで(笑)。三宿という土地柄なんでしょうね。ファッションが好きな方が多く、そういった層にもしっかりアプローチできているのは、ひとつ自信になりました。
綺麗にする、汚れを取り除く、それだけがクリーニングではない
ー 聞きたかったことがあって、クリーニング屋として、汚れた洋服を受け取ったときの正解は、どういったところに設定しているんですか? 汚れを落とすことを目的として強い洗剤を使うことで洋服が磨耗するパターンもあるのかな、と思うのですが。
茂木:これが結構難しいところで。お客さんはあくまで汚れを落としてほしい。という前提で考えるとつまり、一般的なクリーニング屋さんは、汚れを落としさえすれば、それが正解だと思っているんですね。でも僕らとしては、それだけでは不正解なんです。
ー それだけ、では、不正解であると。
茂木:汚れは落ちていても生地の風合いが変化しているようだったら、それはダメなんです。例えば革製品なんかはわかりやすいですよね。レザーのバッグにボールペンの跡がつきました。その部分を削って上から顔料をふって、綺麗になりました。はい、1万円。こんなのはありえないですね。
ー 洋服や生地のことを考えると、洗わない、という選択肢もありますよね。
茂木:そうですね。洗うことによる変化はどうしても避けられませんから。プロならば、もとの風合いを残したまま、なるべく少ないリスクでできることは何か、見極めることがもっとも重要です。一方で、着用から洗濯の一連の流れでできたシワや色落ち、アタリ、生地の磨耗を味とするのか劣化とするのかは、アパレル業界でもさまざまな意見があると思います。
ー 確かに、正解がありませんよね。個人的にはデニムでいうところの色落ち、ヒゲなどと同じなのでは、と思います。
茂木:そうではあるのですが、それを理解してクリーニング屋に持ってくる人と、そうでない人がいるんですよね。そんなときに、結局、クリーニングの根幹にあるのはコミュニケーションなんだなと、この仕事を始めてすぐの頃の想いに立ち返ります。お客さんが1着の洋服に抱いている愛着と悩み、それをどうしたいのかを聞き、最適な方法を提案する。これの繰り返しですね。
ー なるほど。
茂木:ただ、リスクを負わないとならないことも当然あって、そういったときにこれまでの失敗や経験値が活きてきます。
ー 前回までは平気だったけど、今回でダメになる、ってこともありそうですね。
茂木:もちろんあります。ボンディングやコーティングなど、経年で確実に劣化する素材や加工もありますので。普段洋服を買うなかで、そういったケアが難しいものを知っておいて、それを避ける、という選択肢を持つことも消費活動をするうえで重要だと思います。少なくとも僕は、ケアが厄介そうな素材は自分が着るものには選びませんね。

ー ちなみに、茂木さんは普段どういうものを選ぶんですか?
茂木:天然素材のものが多いかもしれませんね。デザインは、何年でも着用できる、飽きがこないものが好きです。洋服のエイジングを見るのが楽しいんですよね。あとは、できるだけ白を選びたいな、と思っています。
ー あ、確かに茂木さん、全身白ですね。
茂木:僕は口がゆるいので、すぐに汚れを付けちゃうんですけど、今日も大事な撮影なのに全身白で来て、しかもさっき気付いたけど、コーヒーこぼしちゃってる(笑)。でも、まあいいや、落とせるし、って。
ー 汚れるのが怖いって理由で白を避ける人も多いように思いますが、自宅での正しい洗濯方法を知れば、選べる洋服の選択肢も増えそうですよね。
茂木:そう思います。そのことを世に普及していきたいと思い、僕らとしても書籍やYouTubeなどに力を入れています。アパレルの販売員さんも、そのあたりの知識を増やしていくと差別化ができて良さそうですよね。最終的に購入するお客さんと対峙して、会話するのは販売員の人ですから。
愛着のある洋服を長く着続けるために

ー いろいろとお聞きしていく中で思ったのですが、洋服を洗う、と考えると、アパレルとクリーニングってそもそもがすごく近しい関係性のはずですよね。
茂木:そうなんですが、業務内容としては、アパレルとクリーニングって基本的には川上、川下の関係で動いていて、接点があるとしたらクレームが発生したときなんですよ。だから、なかなか良い協業、というのが難しくて(笑)。もっと密に連携していけたら良いのにな、と常に思っています。
ー どのような連携が必要だと考えていますか?
茂木:モノづくりをするタイミングからクリーニング屋を混ぜていただくのが一番ベストですね。
ー あ、なるほど。確かに、そうですよね。
茂木:はい。デザイナーの希望するデザインに対して、どのような素材を用いたら洗える洋服になるのか、を意見交換することは、お客さんに1着の洋服を長く着ていただくことにも繋がるんじゃないかなと。
ー おっしゃるとおりかと思います。
茂木:少し脱線するのですが、MARKAWAREのデザイナーの石川さん(編集注:marka、Textなどのデザイナーも手がける石川俊介さん)という方がいるのですが、クリーニング師の資格を持ってらっしゃって。ご自分のブランドの洋服の手入れの仕方をデザイナー自ら発信していて、素晴らしい取り組みだと思いました。
ー デザイナー自らですか。これまでにないですね。クリーニング師、アパレルの販売スタッフが持っていても役に立ちそうな資格ですよね。
茂木:とはいえ、国家資格ですから、ややハードルは高いんですけどね。なので、ファッションソムリエみたいな、洋服を磨耗させない合わせからデイリーケアまでをお伝えできて、汚れない歩き方とか、所作のところも指南してくれるスペシャリスト的なスタッフがいると、お店のブランド価値向上にもなるのかなと思います。
ー それ、すごくいいですね。
茂木:着方や持ち方で、洋服やバッグの寿命ってずいぶんと変わるんです。顧客に良い購買体験をしてもらうために、そういうところに目線を向ける人も増えてくるかもしれませんよね。新しいじゃないですか。ケアや洗濯の知見が深い販売員。顧客が増えそうですね(笑)。そういう知識も含めて、“洋服を知っている”、ということなのかなと思います。
ー 特に高額なものについてはちゃんと教えてもらえると親切だな、と感じます。
茂木:「高いな……」と思って、でも気に入って買ったシャツとかが、大事な場面で自分を鼓舞してくれたり、支えてくれた経験って、洋服好きなら誰もがありますよね。そういう、洋服と共に経験したこと、乗り越えたことが増えれば増えるほど、その洋服が大切なモノになっていくんです。思い入れがあるモノなら、寿命を短くするのを避けるために知っておくべきこと、簡単に実践できることはたくさんあります。そして、僕らはクリーニング屋だから、愛着のある洋服を長く着続けるための選択肢として、存在を認識しておいてほしいです。何かあったら誠心誠意、力になりますから。
おわりに
1着の汚れた洋服を想像し、なぜその汚れを取り除きたいのかを自分に問うてみる。答えは「また着られるようにしたいから」に決まっているのだが、それは、洋服のためを考えての行動であると気が付いた。
汚れた洋服を着ているのだって別に恥ずかしいことではない。でもやっぱり、汚れが綺麗さっぱり無くなった洋服は清々しく、どこか嬉しそうな顔をしているようにも見える。一番嬉しそうな顔をしているのは、自分かもしれないけど。
茂木さんの話を聞いて、そんなことを思った。このインタビューを読んだあなたの、明日からの洗濯が少しでも楽しいものになったら、嬉しいです。
Knit Care
プロの洗濯集団「洗濯ブラザーズ」によるニットの洗濯方法について
ここでは、茂木さんへのインタビューに続けて、『毎日の洗濯が、「嫌いな家事」から「好きな家事」になるように、洗濯の楽しさを伝える活動をしている』という集団・洗濯ブラザーズによるニットのお手入れ方法をご紹介。ぜひチェックしてみてください。
 “ニットに負担のかからない洗濯”とは?
“ニットに負担のかからない洗濯”とは?洗濯ブラザーズ・次男の茂木康之です。普段は、世田谷区三宿でLIVRERというクリーニング屋を運営しながら、週末はポップアップという形で全国各地のアパレルショップへ行き、洗濯のノウハウを伝えています。
「モノカタル」の第5回は、ニットのお手入れ方法について。
スーツなどと同様に、洗濯のハードルがやや高いイメージのあるアイテムかと思います。でも、そんなことはないんです。
というわけで、今回は、なるべく手間をかけず、なおかつニットにも負担がかからないデイリーなお手入れ方法をみなさんにお教えします。
「洗濯ブラザーズ」が考えるデイリーなニットのお手入れ
使用アイテム
「洗濯ブラザーズ」が答えるニットお手入れFAQ
-
Q1. 毛玉ができないようにするには、どうしたらいい?
毛玉の原因は摩擦なので「今日はニットを着ている」と気にかけることで、結構防止することができますよ。たとえば、バッグを肩にかけないようにする、など。
-
Q2. シミが付いてしまったら、どうしたらいい?
Tシャツと同じケアで大丈夫です。中性洗剤でシミを浮かせてから洗濯するようにしましょう。
Q3. 伸びない干し方を知りたい!
平干しネットを使用するとニットの重さで伸びてしまうのを避けられます。持っていない場合は、腕を肩にクロスさせる干し方や、ハンガーを2本使用して1本は肩に、もう1本は裾にかけて干す方法もあります。
-